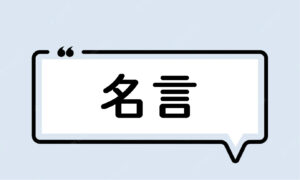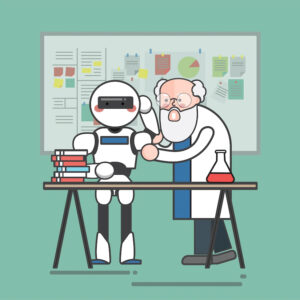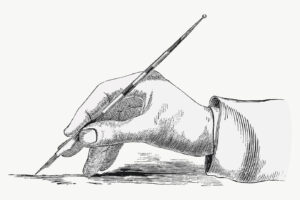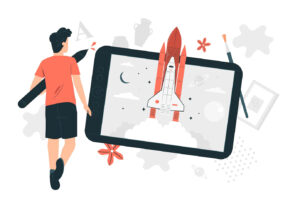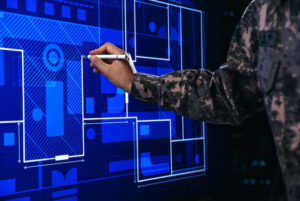偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け
 運営者
運営者ふむ…。
[adrotate banner=”6″]
目次
考察
ラッセルはこうも言った。
その記事にほとんどの詳細は書いた。ニーチェの『虚構と記号』、シャンフォールの『理解できる範囲』然り、人間というものは『ああそういうことね!』というイメージで、早合点してしまうところがある。それには複雑な事情が絡み合っていて、例えば10年前の私の上司だった、5個上の年上の人間だったら、

それはわかってる。
というのが口癖だったわけだが、彼は、自分が年下の私やその同僚よりも無知である、という事実を受け止めることが出来なかった。だからそういう風な言い回しを、こちらの説明の最中に、食い気味に言ってきて、我々に主導権を握らせないように、躍起になっていたわけだ。その早合点の原因は、見栄であり、虚栄心であり、過信であり、嫉妬だ。実に複雑な心情が絡み合って、そうした態度に繋がってしまったのである。
[adrotate banner=”7″]
関連する『黄金律』
あわせて読みたい

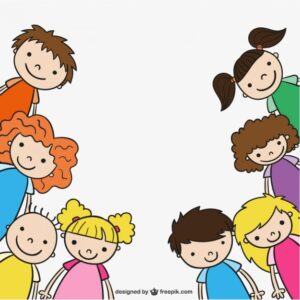
『人の評価に依存することの愚かさを知れ。依存しないなら強い。』
第14の黄金律 『人の評価に依存することの愚かさを知れ。依存しないなら強い。』 人間には、理解できる範囲とできない範囲がある。では、その事実を受け...
同じ人物の名言一覧
あわせて読みたい

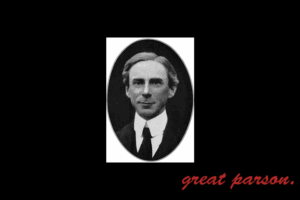
ラッセルの名言・格言一覧
イギリスの哲学者。生誕1872年。男。バートランド・アーサー・ウィリアム・ラッセル(画像) 名言一覧 『諸君が自分自身に対して関心を持つのと同じように、他人が自分...