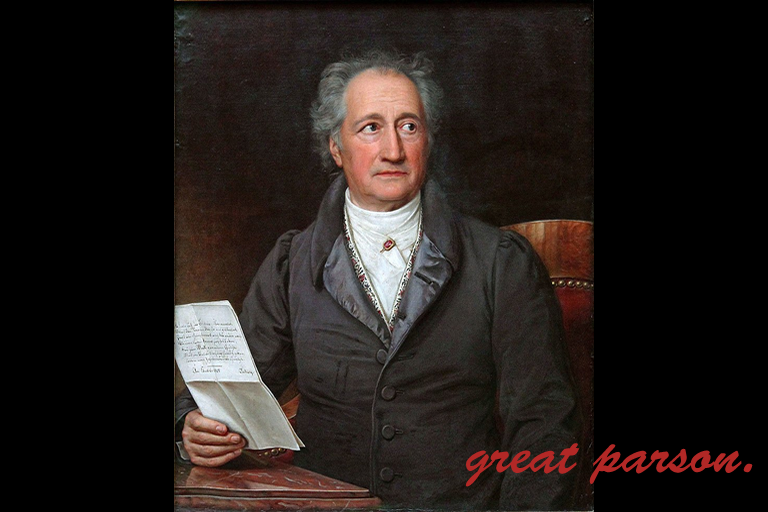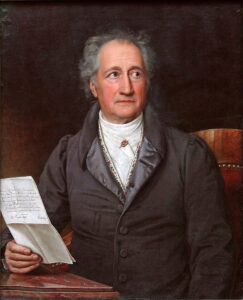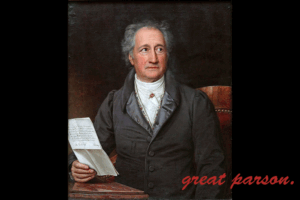偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け
[say name=”偉人” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png”]ドイツの詩人 ゲーテ(画像)[/say]
[say name=”運営者” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/シャーロックホームズアイコン1.png” from=”right”]ふむ…。[/say]
[adrotate banner=”6″]
考察
正直このテーマはくだらないと思ってしまったことと、自分自身がまさにその通りだった為、それに戻らないように(くだらない)とくぎを刺すように思ったことが原因で、この言葉はスルーしようと一瞬思った。つまり私も『刺激を欲した』のだ。むしろ、それだけを欲していたと言っていいほどの少年時代を過ごした。そして多くの失敗をしたし、学ぶことをスルーしてしまった。だからこそ、こんなテーマには、目すら向けてはいけないと思ったわけだ。だがすぐにこう思い直した。
いや、これは自分だけが抱えているテーマではない。少年少女、青年に、往々にして当てはまるテーマなのだ。だとしたらこの言葉と向き合っておこう。ゲーテとて、当然そういう見地でこう言ったはずだからだ。
まず私が思いついたことは『インセンティブ(誘導)』なわけだが、実は私は10代後半の頃、人を動かすとき、その心理を巧みに利用して、つまりこの『インセンティブ』を使って集団を鼓舞したとき、いや確かにその場は大盛り上がりしたのだが、その後、
[say name=”” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png”]あのようにエサで物を釣る様に人を煽るのは良くない。[/say]
と言われた経験があるのだ。その後も、確かにこのインセンティブは大きな力を発揮した。だが、やはりその少年の言う通り、インセンティブで動いた集団は、あくまでもインセンティブが目当てだったわけで、こちらの指揮によって動いたわけではない、という感覚以上にはなれなかったのだ。
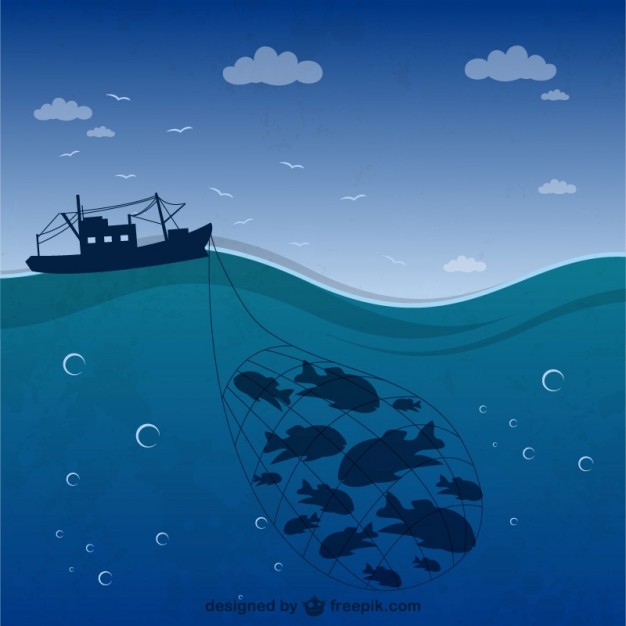
しかしこちらは『ちゃんと指揮(誘導)した』という自覚がある。それが原因でトラブルや不和、行き違いや軽い確執までに発展してしまった。『パブロフの犬』の様に、いくらこの時期の青年たちがインセンティブによって突き動かされるといっても、それに依存させるような教育をするのは、後遺症を伴うことを覚悟しなければならない。
つまり、『ベルを鳴らさなければ動かない』、『エサを与えなければ動かない』ようになるのだ。それは自発的ではない。主体性が育たないのだ。人間に最も必要なのは、この『主体性』だ。
ナポレオンは言った。
青年たちはいつか必ず大人になる。それはつまり、幾多の責任を負い、幾多の試練と直面することを意味する。そんなとき、力になるのは『かつてインセンティブで動いた経験』ではない。『インセンティブに頼らず自ら動き、解決した主体性』なのである。
私はゲーテの言葉で『インセンティブと主体性』というキーワードを思い浮かべた。私も今、もうすぐ30代に突入する部下を6年間見ていて、このテーマはとても身に染みる。確かに、『教えられるのが嫌な彼らの時代に、刺激の経験の中で学んでもらう』ことは、一つの手であり、知恵である。だが、いくら若者が『教えられることより刺激を求める』としても、『主体性』の真逆である『反応性』豊かな、つまりインセンティブ依存の人間に育てないように注意しなければならない。
[adrotate banner=”7″]
関連する『黄金律』
[kanren id=”22904″]
[kanren id=”22911″]
同じ人物の名言一覧
[kanren id=”27792″]