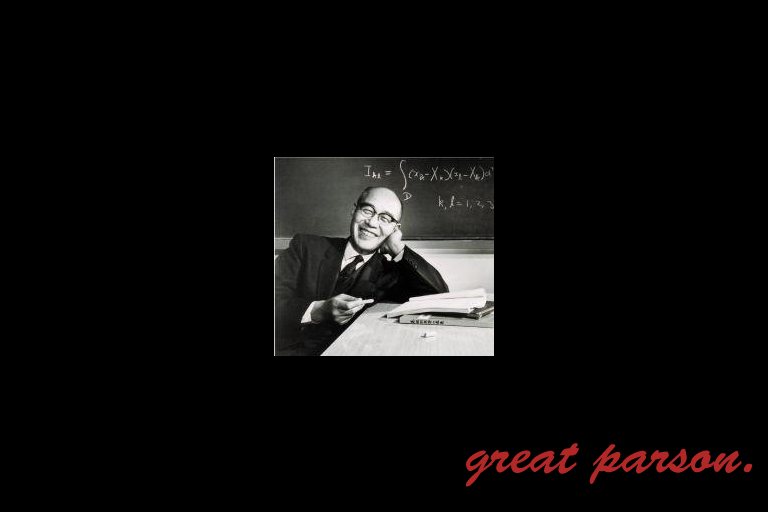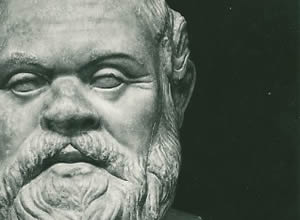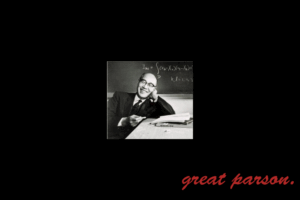偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け
[say name=”偉人” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png”]日本の理論物理学者 湯川秀樹(画像)[/say]
[say name=”運営者” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/シャーロックホームズアイコン1.png” from=”right”]ふむ…。[/say]
[adrotate banner=”6″]
考察
元ニューヨーク市長のルドルフ・ジュリアーニが、『割れ窓理論』を徹底追及し、ニューヨークの犯罪率を激減させることに成功させた。『割れ窓理論』とは、『建物の窓が割れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓も間もなく全て壊される』という現象のことを指示した理論である。これを考えた時、湯川秀樹の言葉の意味は、すぐに理解できるようになる。
孔子の言葉の超訳、
にも書いたが、SMAPの中居正広は、若い頃に『汗かけ、恥かけ、物を欠け』と言われ、肝に銘じて生きてきたと言う。『聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥』という言葉にある様に、我々はかつて、非常識な場所で用を足し、非常識な物を口にした時期を経て、今に至る。その経験があるから、規範意識が固まって成長した今があるのだ。

ある、『実の親に15年以上の間、軟禁されていた子供』は、それが発覚して、学校に通うことになった時、文字が書けない状態だったという。彼らがもし、皆と同じように小学校に通い、中学校に通っていて、そこで失敗し、学習し、経験を積み重ねていたのなら、文字は書けたのである。このことについてじっくりと考えるべきである。
確かに彼らはその母親を訴えることはなかった。彼らなりにその親の愛情をくみ取り、そうして心底から恨むことはできなかったからだ。ただ、その後に学校に通って文字を書く練習をしている様子を見て私は、義務教育の大切さを思い知った。彼らの母親は、子供達に危険な思いをしてもらいたくなかった。カーテンを開けると、
[say name=”” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/女性の人物フリーアイコン素材.png”]外の世界に興味を持つな!外は危険な世界だ![/say]
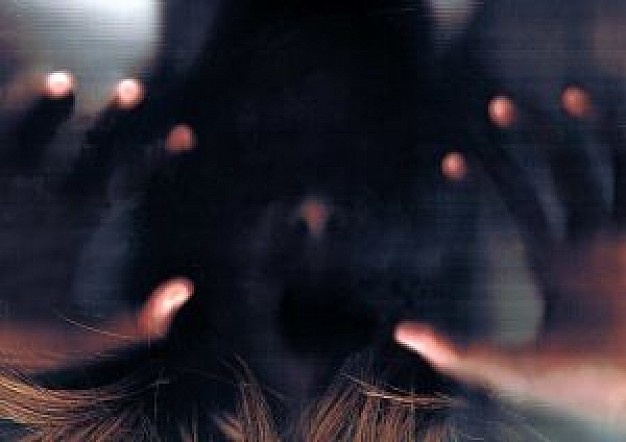
と怒鳴り散らし、外の世界に強迫観念を植え付けたその母親は、彼女なりに彼ら子供のことを、愛していたのだ。しかし、『愛』とは奪うことではなく、与えることだ。彼女は自分が認識する愛のカタチを過信し、彼らの自由を奪った。確かに、その15年の間、社会では大勢の人の命が奪われただろう。だが、彼らはそんな中、生き残ることができた。
ソクラテスは言った。
ソクラテスの考え方に触れると、彼女のやったことが『真の悪』かどうかは首をかしげざるを得ない。
だが、人間はいずれ死ぬのだ。たとえ自分の生きている間その子供たちの命を守ったとしても、自分が死んだ後はどうする。子供たちはどうやって生きていけばいいのか。それとも、『自分が生きている間だけ、子供に生きていてもらえればそれでいい』のか。もしそうなのだとしたら、彼女の愛など大したことはない。
いいんだ。どうせ死ぬんだ。いつ死ぬかはわからない。だが、思う存分この一生を旅してから死ぬべきなのだ。親が子供に教えるべき人生の生き方は、『現実逃避』ではなく、『悔いのない航海』である。

[adrotate banner=”7″]
関連する『黄金律』
[kanren id=”23079″]
[kanren id=”23087″]
[kanren id=”23096″]
同じ人物の名言一覧
[kanren id=”30152″]