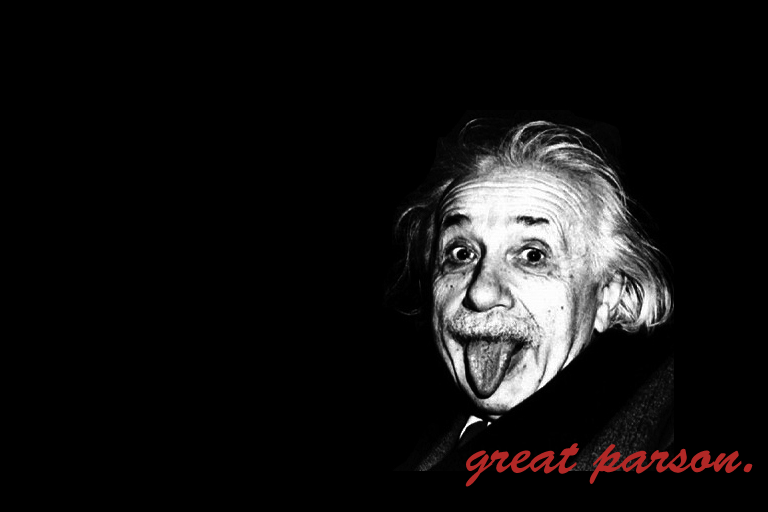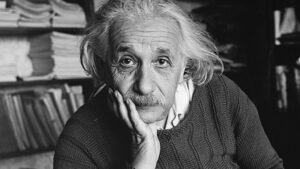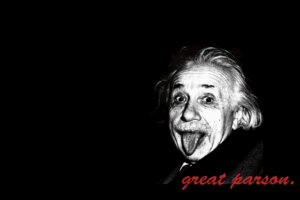偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け
[say name=”偉人” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png”]ドイツの理論物理学者 アインシュタイン[/say]
[say name=”運営者” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/シャーロックホームズアイコン1.png” from=”right”]ふむ…。[/say]
[adrotate banner=”6″]
考察
『神=真理=愛』
だ。この図式だ。それを考えた時、例えばこう実験してみる。大好きなフカヒレのスープがある。大好物だ。滅多に食べられない、高級料理だ。あのトロトロしたフカヒレとアンをスプーンですくって、口に入れた時のあのとろけるような食感。いやあ、贅沢だ。至福の時だ。幸せを感じるのだ。何しろ、大好物を食べているのだ。
では、そのフカヒレを3か月連続で食べてみよう。しかも3食全部。そして、運動と仕事を一切しないで。読書もゲームもダメだ。会もダメ。許されるのはゴロゴロしたり、うろうろするだけだ。そんな中で、そのフカヒレの味の質は、何回目まで保っていられるだろうか。実は、最初そのフカヒレが好きだった理由、そのカギは4つある。
一つ目は、滅多に食べられなかった、ということ。
二つ目は、高級料理という意識があった、ということ。
三つ目は、そこに辿り着くまでに時間がかかった、ということ。
四つ目は、その間に運動や仕事や人生のストレスがあった、ということ。
スノッブ効果とは、希少性が高い商品に対して購買意欲が湧く概念。ヴェブレン効果とは、他人が持っていない高級品を持つことで自己顕示をする概念。ハロー効果とは、後光が差す人間には、パワー、可能性を感じるという思い込み。限界効用の逓減とは、分りやすい具体例をひとつ挙げれば、普通、最初の1杯のビールはうまいが、 2杯目は1杯目ほどうまくない、3杯目は2杯目ほどうまくない。このように1杯目、2杯目、3杯目となるほど、ビール(財)から得られるメリット(効用)は小さくなるということ。

さて、自分の行為、好み、判断の基準が、本当にこれらの心理的効果の影響を受けていないと、断言できるだろうか。つまり、コントロールできているか。さも、10杯目のビールを、仕事終わりの1杯目のあのビールの味の質と同じように、飲むことが出来ているだろうか。こういうことを考えた時、私は『一本の線』が見えるのだ。それが『神』の正体であると考えている。これでも私は、この言葉を言うまでに壮絶なる思索の時間を積み重ねている。
追記:この記事を強化できる記事を書いた。このサイトの集大成である。
[kanren id=”23440″]
[kanren id=”23479″]
[adrotate banner=”7″]
関連する『黄金律』
[kanren id=”22755″]
同じ人物の名言一覧
[kanren id=”26384″]