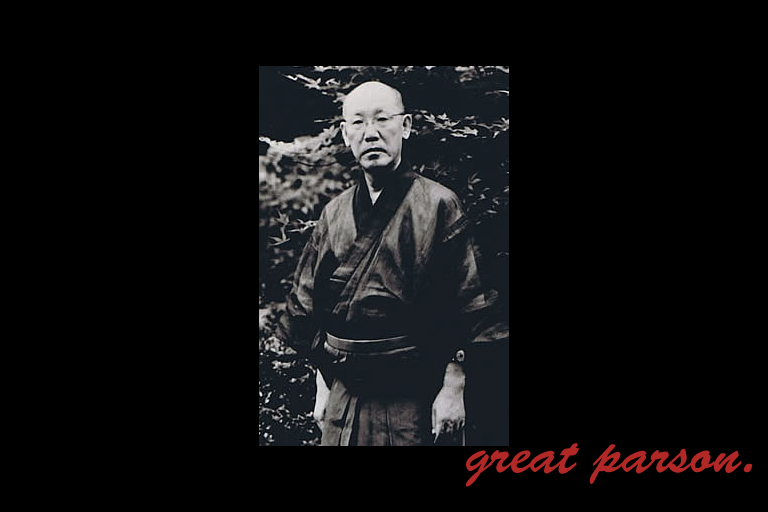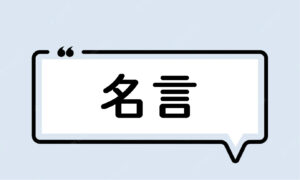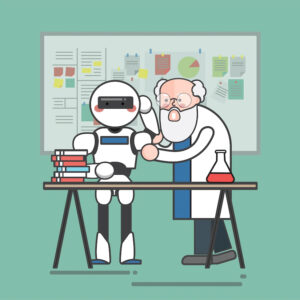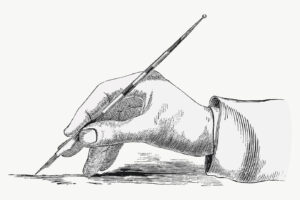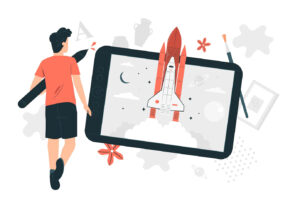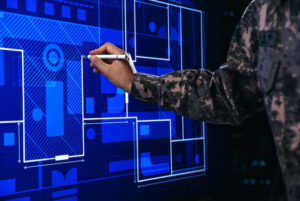偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け
[say name=”偉人” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png”]日本の哲学者 安岡正篤(画像)[/say]
[say name=”運営者” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/シャーロックホームズアイコン1.png” from=”right”]ふむ…。[/say]
[adrotate banner=”6″]
考察
『人間は何事によらず新鮮でなければならない。ところがいかにすれば新鮮であり得るかといえば、やはり真理を学んで、真理に従って生活しなければいけない。もっと突っ込んで言えば、人間としての深い道を学ぶ。正しい歴史伝統にしたがった深い哲理、真理を学び、それに根ざさなければ、葉や花と同じことで、四季に従って常に魅力のある、生命のみずみずしさを維持してゆくことはできるものではない。』
根っこがなければ、葉は生い茂らないし、実は実らない。例えば、お金のことだけで考えてもそうだ。金を『膨張』的に集めることは出来ても、根っこがない人間がそれをやれば、それは刹那のものとして消えてなくなる。私自身がそういう拝金的で刹那的な人間だったからよくわかるのだ。

『義』を軽んじ、『利』にひた走った人間の末路は、決まっているのである。膨張は、弾けるのが相場だ。同じように、あらゆる場面でこの『根っこと枝』の原理は、通用する。例えば、
ブッダは言った。
『木をノコギリで切り倒しても、その根っこが強力なら再びニョキニョキ生えてくる。それに似て、君の心に巣食った欠乏感があまりに強力な呪いであるがゆえ、一時的に落ち着いても根は生きているから、すぐにまたニョキニョキと伸び、苦しくなり、『足りなく』なる。』
よく考えたらわかるが、『何度やってもリンゴが実らない』と言って、『桃が実る枝をその都度切り落とす』という行為は、無知としか言いようがない。全ての根幹は、『根っこ』にあるのだ。根っここそが、根幹なのである。
『不易流行』とは、変えるべきところは変え、変えないべきところは変えない、という教え、戒め、心構え、教訓である。いつまでも変化しない本質的なものを忘れない中にも、新しく変化を重ねているものをも取り入れていくこと。また、新味を求めて変化を重ねていく流行性こそが不易の本質であること。
つまり、常にみずみずしく、新鮮であり、不易(変わらぬまま)でいるということは、流動変化させる柔軟性を持っている必要がある。しかし、ただ流動変化しているだけでは、流されているだけだ。そんな中、『真理という圧倒的な根っこ、本質』を押さえている人間は、そうではない。彼らは流されているわけではないのだ。主体性がある彼らは、『流動変化する姿こそ真理だ』ということをわきまえているだけであり、それに柔軟に合わせにいっている。
小津安二郎は言った。
流動変化することに対し、主体的か、反応的か、ということが、極めて重要なのである。
[adrotate banner=”7″]
関連する『黄金律』
[kanren id=”22588″]
同じ人物の名言一覧
[kanren id=”30126″]