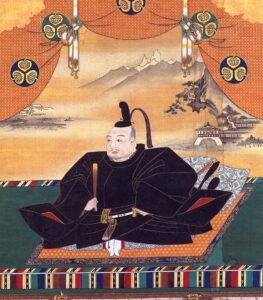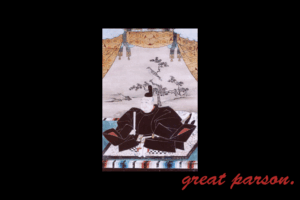偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け
[say name=”偉人” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/戦国武将のアイコン.png”]日本の武将 徳川家康(画像)[/say]
[say name=”運営者” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/シャーロックホームズアイコン1.png” from=”right”]ふむ…。[/say]
[adrotate banner=”6″]
考察
徳川家康はこうも言う。
家康は、3歳にして母と別れ、 6歳にして人質に出され、自分の実の娘と妻を殺害せざるを得ない、苦難を強いられた。それが『栄誉ある勝利』かどうかは、少し考えればわかるはずだ。彼が歩いた道のりとは、『修羅』そのものだったのである。

『そんな道』を歩いてきた家康には、ある『人生の黄金律』が見えていた。『勝って兜の緒を締める』という、人生の教訓を、誰よりも思い知っていたのだ。
『レジリエンス』とは、どんな境遇になっても、平常心を忘れず、足元をすくわれないように努めることが出来る能力。家康には、それがあった。『勝って驕らず、負けて腐らず。』の重要さを、身を持って理解していたのだ。
アリストテレスは言う。
そして、渋沢栄一は名著『論語と算盤』で『得意時代と失意時代』という概念について書いている。
およそ人の禍は、多くは得意時代に萌すもので、得意の時は誰しも調子に乗るという傾向があるから、禍害はこの欠陥に食い入るのである。ならば、得意の時だからといって気をゆるさず、失意の時だからとて落胆せず、平常心を保つことを意識することが重要である。
道教創案人物の老子も、
と言ったが、勝ち逃げしている人間はもちろん、そもそも、勝った負けたで一喜一憂しているようでは、レジリエンスに欠ける。それすなわち、『失意時代』への悪しき布石なのである。また、私の知り合いに『勝ち逃げ』に執着している人間がいた。彼は常に勝ち続けていないと自分のアイデンティティが崩れてしまうという強迫観念に襲われていて、周りから見たらとても必死で、躍起になっている。
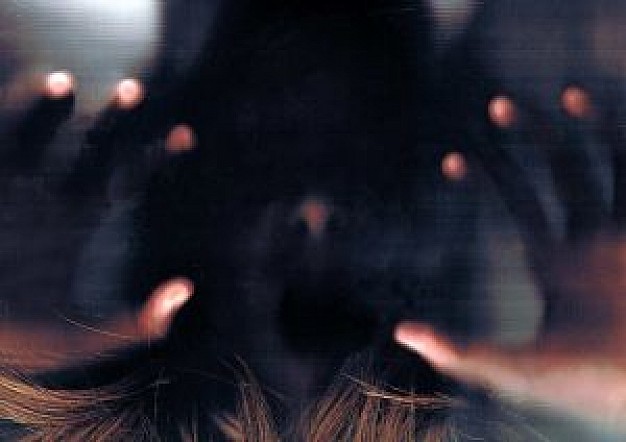
事実、『勝てる勝負しかしない』彼を見て、周りの幾人かは短絡的にそれを高く評価するのだが、そんな彼らも時間を重ねていくごとに彼の器が小さく、自己中心的であるということを理解していき、そのうち距離を置くようになる。
彼は、『ホームとアウェイ』であれば、ホームに依存するような人間だった。アウェイを避けるのだ。アウェイだと自分の本領が発揮できない。負けてしまうこともある。それだと恥をかく。勝ち続けてきたからこそ今の自分があるというある種のジンクスが崩れてしまう。
しかし、人間が真の成長を遂げることができるのは、アウェイだ。アウェイに自ら身を置いて、負け続け、そこから何度も何度も立ち上がることで不撓不屈の精神を身につけることができる。上に書いたレジリエンスたる能力というものも、そうした苦境を乗り越えた人間だけが持つことができるものなのだ。
勝ちにこだわりすぎると傲慢不遜に陥り、あるいは真の成長を遂げるための機会損失を起こす。そして、『本当の勝負所』で負けてしまうという本末転倒な事態を招く結果になる可能性がある。そのことについて理解するべきである。
[adrotate banner=”7″]
関連する『黄金律』
[kanren id=”22854″]
同じ人物の名言一覧
[blogcard url=”https://www.a-inquiry.com/tokugawaieyasu/”]