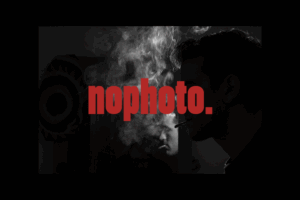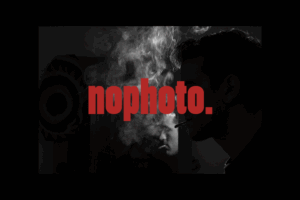偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け
[say name=”偉人” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png”]日本のプロテニスプレイヤー 松岡修造[/say]
[say name=”運営者” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/シャーロックホームズアイコン1.png” from=”right”]ふむ…。[/say]
[adrotate banner=”6″]
考察
私も小学生の頃を思い出すと、人と同じことをしなければ、そのグループから疎外され、孤独を味わうことになる可能性があることを危惧し、自分の個性を押し殺して、相手に合わせ、人と共感することを楽しむ時期があった。
だが、私の場合は割と早い時期から、自分の意志を強く燃やして、周りと対立する覚悟を持つ方向に、思慮が傾いていた。小学校の頃に軽い虐めのようなものがあったが、今思い出しても、別にあれは『虐め』ではなく、『喧嘩』という印象が強い。だが、あのときにもし私がその力に屈して、塞ぎ込んでしまって衰退してしまうようであれば、あれは『虐め』となっただろう。
私はその後すぐに別の友人と手を組み、勢いをつけた。相手は女だったし、殴り合って喧嘩をするということはなかったから、別にそのまま、気持ちさえ強く持っていれば大丈夫だと考えて、それを貫いた。すると気がついたらそういう不穏な空気は終わっていた。
両親がクリスチャンで、私はそうじゃない、という事実も強く関係していた。そうした事実が、(俺は俺。親は親なんだ。)という意識を私に強く根付かせ、自我が発達していき、そうした他との対立を覚悟できる人間にさせていったのだ。だからこの松岡修造の言葉をもし私にかけるなら、そうした時期よりも、もっと前の時期だ。小学校低学年か、それ以下か。
私は苦しんでいた。最愛の親と、生きる価値観が違うことを知ったからだ。受け入れることが出来なかった。それだけ親を、愛していたということだ。それだけ親が、愛してくれていたとうことだ。それだけに、その愛の形がいびつである事実が、胸に深く突き刺さった。

人と同じであることは、とても安心する。だからその方向に思慮が傾いてしまうことは、私にはよくわかる。だが、人間はこの世に一人で生まれ、一人で死んでいくのだ。そこには確かに両親の存在が欠かせないのは事実なのだが、その両親も、死んでいくときは、一人で死んでいく。
ヘルマン・ヘッセは言った。
たった一度のこの人生を、この唯一無二の人生を、それぞれが、悔いの残らないように生き貫くべきである。
[adrotate banner=”7″]
関連する『黄金律』
[kanren id=”22690″]
[kanren id=”22706″]
[kanren id=”22732″]
[kanren id=”22746″]
同じ人物の名言一覧
[kanren id=”29712″]