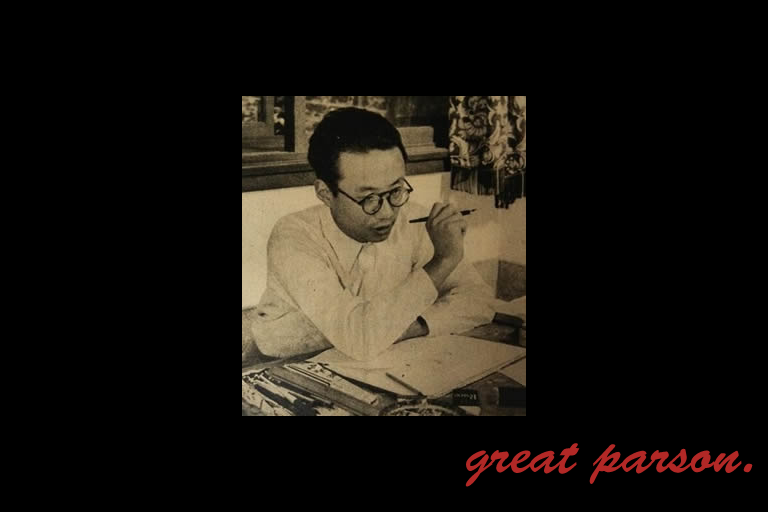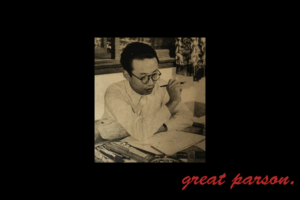偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け
[say name=”偉人” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/漫画家のアイコン1.png”]日本の漫画家 手塚治虫(画像)[/say]
[say name=”運営者” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/シャーロックホームズアイコン1.png” from=”right”]ふむ…。[/say]
[adrotate banner=”6″]
考察
そもそも、『面白い』と感じるシーンは、読み手によって千差万別である。日常的な何気ないうっかりミスが面白いと思う人もいれば、そんなことでは満足せず、おやじギャグや、一発逆が連発するギャグマンガが面白いと言う人もいる。更に言えば、人の首が簡単に跳ねたりするうくらい刺激出来ではないと、面白いとは思わないという人もいる。ということで、十人十色だ。それが虚ろな人間の感情というものである。
だとしたら、その『どれ』に照準を合わせて描けば『面白い漫画』を作れるかということになる。もちろん、その一つ一つに絞って、ユーザー層をターゲティングし、コアな顧客を獲得するという戦略もあるだろう。
しかし例えば『結果論』的なイメージで、
(あの漫画は、読んでいる最中、別に対して笑いは無かったのだが、どうも心に残って、次の作品も見たくなるんだよなあ)
という感覚を読み手に植えつかせる様な、ここで言う『教科書』のような作品は、とても『面白い』作品である。
何しろ『面白い』というのは『ユニーク』という意味で、『ユニーク』というのは違う意味で『たった一つ、唯一』という意味でもあるわけだが、どこにでもありそうな容易なギャグマンガを描いて、短絡的に笑いを誘って、『面白い』と思わせるのではなく、『ユニークさ(唯一無二)』のずば抜けた見解で持って、真理を突き、妙に説得力があって、自然と内省を始めてしまうようなテーマを描き、終わった後に心に残って、消えず、読み手の糧になるような、そういう漫画はとても、『面白い(ユニークな)』作品である。
安易な面白さを追求したのではなく、『ユニークさ』を追求して描かれた漫画は、数十年経っても心に残って、消えることは無い。私がそうだ。彼の『ブラック・ジャック』のことは、永久に忘れないだろう。20年経った今、内容そのもの自体は、あまり覚えていない。しかし、あの漫画が、それを通して世に何を訴えたかったか、という深遠なテーマは、当時小学生だった精神未熟な私が判断しても鮮烈で、今も尚心に残って、消えないのである。

私も本当にたくさんの漫画を読んできた方だ。だが、手塚作品ほど自分の心にえぐって入り込んだ作品は、そうなかった。そういえば、今私の手元には、手塚治虫の『ブッダ』のDVDがレンタルされて、置いてある。この様にして、人生を真剣に生きるようになった今、無意識に手を伸ばしている。これが、手塚治虫の『教科書』たる所以なのかもしれない。
[adrotate banner=”7″]
関連する『黄金律』
[kanren id=”22904″]
[kanren id=”22911″]
[kanren id=”22923″]
同じ人物の名言一覧
[kanren id=”28657″]