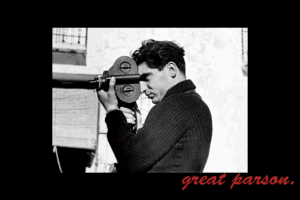偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け
[say name=”偉人” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png”]イギリスのミュージシャン シド・ヴィシャス[/say]
[say name=”運営者” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/シャーロックホームズアイコン1.png” from=”right”]ふむ…。[/say]
[adrotate banner=”6″]
考察
音楽というものを真剣に考える人は、音楽が心底から好きな人だ。いや、好きな人というよりも、何かこう、その枠を飛び越えて、『音楽』という概念が生み出された起因まで遡って思慮を巡らせ、何とかしてそのエッセンス(本質)を得ようとするような行為からは、まるで、自分と音楽を一心同体にしようとするような、ある種の宗教にも似た、芸術的な情熱を燃やす人だ。

私は彼の様に、音楽に命を捧げるような道は選択しなかったが、あんなにも10代の頃に歌って騒いで、という日々を繰り返していたのに、あるときから、カラオケにパタリと行けなくなった。虚しくなったのだ。自分がそこで音楽を『浪費』している様な気がして、その行為自体に疑問を覚えるようになったのだ。歌というものは、音楽というものは、本来、もっと崇高で、心底を振るわせるような、感慨深いものだった様な気がしたのだ。それが、カラオケではそうはならなかった。それはまるで、音楽の浪費であるかのような感覚に襲われるようになったのだ。
その後、堂本剛が平安神宮でやったコンサートを撮った映画、『平安結祈』を観たり、天才ピアニストが、『音楽は毎回違う顔を見せてくれる。私の奏でる音楽は毎回全て違います。』と言っているのを聞いたりして、兼ねてから引っかかっていた私の感覚と、繋がっていくような感覚を得ていった。
その正体は『アウラ』だった。アウラとは、『一度きりの要素』ということ。私が『音楽の浪費』と感じていた音楽に対する疑問と、その『アウラ』の概念が結びついたとき、私は、音楽が誕生した起因に触れた気がしたのだ。

我々の命も、音楽も、同じく、『アウラ』である。その姿形が人から見てデタラメに見えても、結局一つの、『アウラ』である。音楽は、アウラでなければならない。音楽も命も、アウラだからこそ、厳かで尊いのだ。シド・ヴィシャスの言葉で、そんなイメージを頭に浮かべた。
[adrotate banner=”7″]
関連する『黄金律』
[kanren id=”22706″]
[kanren id=”22732″]
[kanren id=”22746″]
同じ人物の名言一覧
[kanren id=”27947″]