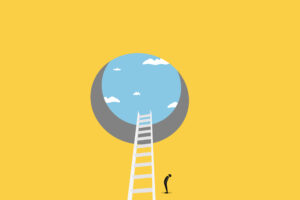・NEXT⇒(一致する偉人の名言)
・⇐BACK(簡潔に)
更なる詳細を追求する
ひとつのことに打ちこむ
松下幸之助から『経営の神』の異名を受け付いだ現代の経営の神、稲盛和夫の著書、『心を高める、経営を伸ばす』にはこうある。
ひとつのことに打ちこむ
私は、一つのことに打ちこんで、それを極めることによってはじめて真理に達することが出来、森羅万象を理解することが出来ると思います。たとえば、長年仕事に打ちこみ、素晴らしい技術を習得した大工さんなどに人生について聞くと、素晴らしい話をされます。また、修行をし、人格を磨いてきたお坊さんは、異分野の話をしても素晴らしい真理を説かれます。その他にも作家、芸術家など一芸を極めた人の話には、非常に含蓄があります。
(中略)広く浅く知ることは、何も知らないことと同じなのです。深く一つのことを探究することによって、すべてのことに通じていくのです。
一つのことに集中するということについて、これだけの偉人たちの意見の一致があることは、想定外だった。
『稼ぐ人』の普遍の法則。関係性と拡張性、そして一貫性
有名スポーツ選手から経営者まで年収1億円を超えるクライアントを50名以上抱える富裕層専門のカリスマ・ファイナンシャル・プランナー、江上治の著書、『年収1億円思考』にはこうある。
『稼ぐ人』の普遍の法則。関係性と拡張性、そして一貫性
『売れる人(商品)の法則』をまとめて言うと、『関係性と拡張性、そして一貫性』となろう。これが『稼ぐ人』のキーワードである。(中略)マーケットとの関係性は強固であり、そこを深く深く掘り下げ、集中的に時間とお金を使って事業を拡張している。(中略)全てが創業以来、一貫しているのである。この一貫性は、時間軸を長く持てば持つほど、信頼が生まれる。(中略)儲かっても浮気せず、本業に徹する。本業を深く深く耕す。それもまた、成功の重要な要件なのである。
多くの人がこうして口を揃える。しかし、確かに物理的に考えたって同じ場所に水がしたたり落ちていたら、長い時間をかけてそこに穴が空き、あるいは大河となるのだから、その通りだったのだ。
勉強とは自分の剣を磨くこと
秋元康の著書、『企画脳』にはこうある。
勉強とは自分の剣を磨くこと
当然だが、ただむやみに勉強すればいいというものではない。大切なのは、自分にとって何が専門分野なのかを見極めることだ。専門分野とは、闘うために磨いた自分の『剣』を持つ、ということである。
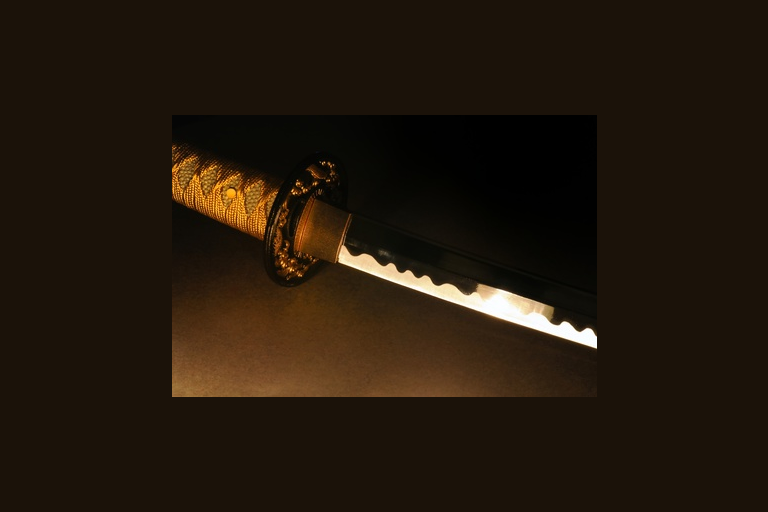
『簡潔に』に剣の話を書いたが、これは別に秋元康の言葉を引用したわけではない。偶然一致しただけだ。
時間を価値あるものに集中して使う
自己発見に関する世界最高の権威の一人、ロビン・シャーマの著書、『3週間続ければ一生が変わる』にはこうある。
時間を価値あるものに集中して使う
先日、わたしのオフィスにフェデックスの宅配便が届きました。なかに入っていた封筒には、金の封印がしてあり、表には私の名前がていねいに書かれていました。(中略)ある大企業のCEOからの手紙で、会議に出席する単にヨーロッパへ向かうとき、空港で私の著書を買ってくださったのです。
(中略)彼は手紙にこう書いていました。(中略)わたしは誓ったのです。気を散らす多くのことを生活から排除して、基本的なことだけに集中しよう。仕事のやり方と生き方に変化をもたらす力をもっている数少ない活動だけに絞り込もう、と。(中略)『なんでもしようとする者は、結局なにも達成できない』ということを思い出すようにしています。そのシンプルな哲学を実践し始めてから、わたしの生活がいかに向上したかは、とても書きつくすことはできません。ありがとうございました。
時間はもっとも貴重なものですが、ほとんどの人は世界中の時間を所有しているかのような生活を送っています。生活をコントロールする秘訣は、一日一日の中で集中する感覚を取り戻すことです。ものごとを成し遂げる秘訣は、なにに手を付けずにすますかを知ることです。人生の使命をはたしてなにかを遺せるような強い影響力がある活動と優先事項だけに日々の時間を使う様になれば、すべてが変わるでしょう。
歴史上の偉大な思想家の多くも、おなじ結論に達してします。孔子はこんなふうに言っています。
『二兎を追う者は一兎をも得ず。』
ローマ時代の哲学者、アウレリウスは、
と言いました。経営学の権威であるピーター・ドラッカーは、この叡智について別に表現をしています。
一つに集中するのだ。『別々の方向に走り抜けた二匹の兎』を同時に捕まえることはできない。
ハリネズミの概念
『ビジョナリーカンパニー② 飛躍の法則』にはこうある。
ハリネズミの概念
読者はハリネズミだろうか。それともキツネだろうか。アイザイア・バーリンは、有名な随筆『ハリネズミとキツネ』で、世間にはハリネズミ型の人とキツネ型の人がいると指摘した。これは古代ギリシャの寓話、『キツネはたくさんのことを知っているが、ハリネズミはたった一つ、肝心要の点を知っている』に基づいたものだ。
キツネは賢い動物で、複雑な作戦をつぎつぎに編み出して、ハリネズミを不意打ちにしようとする。昼も夜も、ハリネズミの巣をうろつき、完璧の機会をとらえて襲い掛かろうとしている。キツネは動作が俊敏で、毛並みが美しく、足が速く、頭がよく、ハリネズミごときに負けるはずがないと思える。対するハリネズミは何とも冴えない動物で、ヤマアラシとアルマジロの子のような姿形だ。短い足でちょこちょこと歩き、エサを探し、巣を守るだけの単純な生活を送っている。
キツネはハリネズミの通り道のすぐ近くにひそんで、息を殺している。ハリネズミはエサ探しに熱中していて、キツネの狙い通りの場所にやってくる。『よし、今度こそ仕留めてやる』。キツネは地面を蹴って、目にもとまらぬ速さでとびかかる。

ちっぽけなハリネズミは殺気を感じ、目をあげる。『またまたお出ましだ。何度失敗しても懲りない奴だなあ』。身体を丸めて、小さな球のようになる。鋭い針がどのよう公にも突き出している。獲物を目の前にしたキツネは、ハリネズミの防御態勢をみてとびかかるのを諦める。
だが森の中に引き返しながら、もう次の作戦をあれこれ考えている。ハリネズミとキツネの戦いは毎日、少しずつ形を変えて繰り返される。キツネの方がはるかに知恵があるのに、勝つのはいつもハリネズミだ。

勝つのは器用貧乏なキツネではない。一つのことに特化したハリネズミだ。
弾み車効果と悪循環
本にはこうもある。
弾み車効果
飛躍を遂げた企業は、単純明快な事実を知っている。つねに改善を続け、業績を伸ばし続けている事実に、きわめて大きな力があることを知っているのだ。当初はいかに小幅なものであっても、目に見える成果を指摘し、これまでの段階が全体のなかでどのような位置を占めているかを示し、全体的な概念が役立つことを示す。
このようにして、勢いがついてきたことを確認でき、感じられるようにすれば、熱意をもって参加する人が増えるようになる。われわれはこれを『弾み車効果』と呼ぶようになった。(中略)飛躍した企業は、当初は大きな目標を公表していない場合が多い。まずは弾み車を回しはじめる。理解から行動に、一段ずつ段階を踏んで、一回転ずつ回していく。弾み車に勢いがついてから、周囲の人たちにこう話す。『この動きを続けていけば、何々が達成できないと考える理由はない。』
※それに比べて『悪循環』とは、決定的な行動、壮大な計画、画期的な技術革新、魔法の瞬間など、苦しい準備段階を飛び出し、突破段階に一気に進む方法を探し求めている。そしてすぐにそれをやめて方針を変え、また逆の方向に押し始める。右往左往を繰り返し、持続的な勢いを作り出せないまま、永久に著しい結果を捻出することはできない。
確かにそうなのだ。冷静に考えると、これらの話は全てその通りなのだ。特にこの『弾み車効果と悪循環』は、私がこの『悪循環』の代表者の様なものだったから、この事実を知った時は、衝撃的だった。私は過去を悔いることはしない方だが、もし、私がもっと前、10代になる前からこの話を知っていたなら、と、考えたものである。
『情熱』と『粘り強さ』を持つ人が結果を出す
ペンシルベニア大学心理学教授で、『天才賞』と言われるマッカーサー賞を受賞した教育界の権威、アンジェラ・ダックワースの著書、『GRIT やり抜く力』にはこうある。
『情熱』と『粘り強さ』を持つ人が結果を出す
(省略)つまり顕著な功績を収めた人たちはみな、粘り強さの鏡のような人だったのだ。なぜそこまで一心不乱に、仕事に打ち込むことができたのだろうか?そもそも彼らは、自分の目指している大きな目標に、簡単にたどり着けるとは思っていなかった。いつまでたっても『自分などまだまだだ』と思っていた。まさに自己満足とは正反対だった。
しかしそのじつ、彼らは満足しない自分に満足していた。どの人も、自分にとってもっとも重要で最大の興味のあることをひたすら探求していた。そして、そんな探究の道のりにーその暁に待ち受けているものと同じくらいー大きな満足を覚えていた。つまらないことや、イライラすることや、つらいことがあっても、あきらめようとは夢にも思わなかった。彼らは変わらぬ情熱を持ち続けていた。
(中略)このように、みごとに結果を出した人たちの特徴は、『情熱』と『粘り強さ』を併せ持っていることだった。つまり『グリット(やり抜く力)』が強かったのだ。
(中略)3番目の答えの人は『やり抜く力』が強い
自分の最重要の目標をとおして世の中の役に立てる人は、本当に幸福だ。そういう目標を持っている人は、どんなにささいなことや退屈な作業にも、意義を見出だすことができる。ではここで、『レンガ職人』の寓話を例に考えてみよう。ある人がレンガ職人に『なにをしているんですか?』とたずねた。すると、三者三様の答えが返ってきた。
1番目の職人は『レンガを積んでるんだよ』。
2番目の職人は『教会をつくっているんだ』。
3番目の職人は『歴史に残る大聖堂を造っているんだ』。
1番目のレンガ職人にとって、レンガ積みはたんなる『仕事』にすぎない。2番目の職人にとって、レンガ積みは『キャリア』。3番目の職人にとっては、レンガ積みは『天職』を意味する。多くの人は3番目の職人のようになりたいと思いつつ、実際のところ、自分は1番目か2番目だと思っている。

『グリット(やり抜く力)』。
まさにそれは、36、37、38の黄金律を総合して言い表した言葉である。
木を割るのを好む人
東京大学理学部、法学部を卒業した、理学博士、茂木健一郎の著書、『アインシュタインと相対性理論がわかる本』にはこうある。
ただし、粘り強く考えたからといって、必ず結論が出るわけではない。生涯をかけても答えを導き出すことができない場合もある。だから、多くの人は、すぐに答えの出る方向に行こうとする。アインシュタインはそれに対して、こんなことを言っている。
『僕には、木を割るのを好む人が多いわけがわかる。こういう仕事だと、結果をただちに見ることができるからね』
アインシュタインの粘り強さは、『木を割る』のとは対極だった。答えが見えなくても意に介さない。何ヶ月も、何年も、あるいは何十年も考え続ける。彼のことを、生涯ずっと一つのことを考え続けた人と言ってもいいだろう。一つのこととは、『目に見えない宇宙の秩序をいかにして数式で書くか』である。
たった一つのことを生涯をかけて考え抜いたところに、アインシュタインの天災生徒非凡さを見ることができる。自然環境の問題として、『持続可能性』が注目されているが、生態系と同じように、思考もまた、続けてこそ、その中にさまざまな果実を育むことができる。粘り強く考え続けることが『持続可能性』となって、天才の発想を育んでくれるのだ。
アインシュタインは一つのことを集中した。そして人類史上に残るとてつもない発見をしてみせた。
成果が見えなくても続ける
儒教、仏教、道教を深く学び、足りない部分を補って創り上げた、洪自誠(こうじせい)の著書であり、川上哲治、田中角栄、五島慶太、吉川栄治ら昭和の巨人たちの座右の書である、『中国古典の知恵に学ぶ 菜根譚』にはこうある。
成果が見えなくても続ける
よいことをしても、その成果が見えないことがある。だからといってやめてしまってはいけない。たとえ今は目に見える形で成果が出ていなくても、草むらに隠れ知らぬ間に実を結ぶ瓜のように、気づかないところできちんと実を結んでいるはずだ。逆に、悪いことをしても、それで得た利益や成果を没収されずにすむことがある。しかし、悪行で得たものというのは、春先に庭に積もった雪のように、たちまち消えてしまうものだ。
粘り強く努力を続ける
また本にはこうもある。
粘り強く努力を続ける
のこぎりでなく縄を使っても、長い時間をかけて木をこすれば、のこぎりと同じように木を切ることができる。雨だれでも、長い時間同じところに落ちれば、石に穴をうがつ。人としての正しい道を学びたいと思えば、このように粘り強く努力を続けなければならない。また、水が流れれば、そこに自然と溝ができ、売りが熟すと自然にへたが落ちる。人としての正しい道を究めたいと思えば、このように自然と道が開けて来るのをじっくり待つべきである。
なかなか結果が出ない。大丈夫だ。それは皆一緒なのだ。重要なのは、『それで、どうするか』だ。
製品ライン拡張の法則
世界的に知られるマーケティングの戦略家、アル・ライズとジャック・トラウトの著書、『マーケティング22の法則』にはこうある。
製品ライン拡張の法則
ラインの拡張は効果がないということが分かっていながら、各社は次々とライン拡張ブランドの出し続けている。以下はその実例の一部である。
- アイボリー・ソープ⇒アイボリー・シャンプー
- ライフ・セイバーズ・キャンディー⇒ライフ・セイバーズ・ガム
- ビック・ライターズ⇒ビック・パンティーストッキング
- シャネル⇒男性用シャネル
- タンカレイ・ジン⇒タンカレイ・ウォッカ
- クアーズ・ビール⇒クアーズ・ウォーター
- ハインツ・ケチャップ⇒ハインツ・ベビー・フード
(中略)拡張ブランドは、いずれも首をかしげたくなるような商品ばかりだ。(中略)『少ないこと』は『多いこと』に通じる。もしあなたが、今日ただいま成功することを望むのであれば、顧客の中に一定の地歩を築かなければならないし、そのためには焦点を絞り込む必要がある。
『製品ライン拡張の法則』とは簡単に言えば、『二兎を追う者は一兎をも得ず』ということだ。
拡張の法則
同じくアル・ライズとローラ・ライズの著書、『ブランディング22の法則』にはこうある。
拡張の法則
ブランドの力はその広がりに反比例する
シボレーはアメリカで一番よく売れる車だった。例えば、1986年、ゼネラルモーターズのシボレー事業部は117万8839台の車を販売した。しかし万人向きの車にしようとしたために、ブランドの力が損なわれた。今日、シボレーの販売第者数は年間100万台以下で、市場ではフォードに次ぐ二番手に成り下がっている。

これも『製品ライン拡張の法則』と同じことだ。
収縮の法則
本にはこうもある。
収縮の法則
フォーカス(焦点を絞り込む)するとき、ブランドは強力になる
スターバックス・コーヒー
ほんの数年間のうちにスターバックスはアメリカで最もよく知られ、人気のあるブランドの一つになった。焦点を絞りこむことは商品ラインを限定することと同じではない。スターバックスは30種類ものコーヒーを提供しているのである。(中略)自家用ジェット機を3800万ドルで購入すれば、あなたの企業は成功するだろうか。そんなはずはあるまい。ブランドを拡張すれば成功するだろうか。もちろんそんなはずがあるわけがない。
もし金持ちになりたければ、お金持ちの人達が金持ちになる前にしたことをしなくてはならない。金持ちになる為に彼らが何をしたかを見つけなくてはならない。自分の会社を成功させたければ、成功した企業が成功する前にしたことをしなくてはならないのである。

拡張させた方が良いのか。それとも収縮させた方が良いのか。よく目を凝らして辺りを見渡してみるといいだろう。
信用力の法則
本にはこうもある。
信用力の法則
あらゆるブランドの成功のカギを握る要素は本物訴求である。記者がレンタカーの記事を書くとき、まずハーツに電話する。記者がコーラの記事をまとめるときは、まず例外なくコカコーラに電話するだろう。記者がコンピュータソフトの記事を書くときは、多分マイクロソフトに電話するはずだ。
(中略)信用力の威力は毎日の生活の中にも見受けられる。新しいレストランがほとんど空席であるためにその店を立ち去った経験を何度お持ちだろうか。ほとんどの人が空っぽの店で食事するよりも込んだレストランで席を待とうとする。その店が本当によいと思えるなら、ドアの外にまで行列ができるだろう。これが信用力の威力である。
この信用力のパワーを身にまとう為にはどうすればいいか。拡張すればいいのか。集中すればいいのか。
一貫性の法則
本にはこうもある。
一貫性の法則
ブランドは一夜では築かれない。成功は何年単位ではなく、何十年単位で測定される。あなたは自分のブランドの境界ををハッキリと限定すべきである。これがブランディングの基本だ。あなたのブランドは人々の頭の中で単純にして絞りこまれた何かを表していなくてはならない。このような限定こそがブランディング・プロセスの本質的なポイントである。(何年単位ではなく、何十年にもわたる)一貫性を伴った境界の設定によってブランドは構築される。ローマは一日では築かれなかった。

拡張せず、収縮し、一貫し、信用力を得る。つまり、一つのことに集中して得られることの恩恵は、甚大である。
天才と障害
また、『脳とカラダの不思議』にはこうある。
天才の中には障害のある脳の持ち主も多い?
『天才』と呼ばれる人々の中には、意外にも脳の疾患を持った人物が少なくない。例えば、発明王エジソンは、注意欠陥多動性障害で落ち着きがなかったため、小学校を退学させられたという逸話が残っている。また、レオナルド・ダヴィンチやアインシュタインも学習障害をもち、幼い頃は読書や計算が苦手だったといわれる。
歴史上の人物だけでなく、近年は自閉症など知的障害をもつ人が、特定の分野において天才的な才能を発揮することを意味するサヴァン症候群という言葉を耳にするようになった。曲を一度聴いただけで、まったく同じに演奏できる人や、まだ幼いこどもが遠近法を使ったリアルな絵を描く、猛スピードで通り過ぎる列車のなかに有蓋車両が何台あったかを正確に言い当てる、カレンダーの日付をみただけで、その日が何曜日なのかを正確に言い当てる…など、才能は症例によって異なるが、彼らに共通しているのはその驚くべき記憶力である。脳の中にまるで写真機やボイスレコーダーがあるかのように、見たもの聞いたものを正確に記憶することができるのである。
それは言語(概念)として物質を理解しているのではなく、直感像として脳に焼き付けるからだともいわれている。言葉やコミュニケーション能力などにハンディキャップをもって生まれた人々は、大人になっても言語能力を開花させることができない。それゆえに、ほかの脳の部位が飛躍的に発達し、その結果こうした能力を身につけることになったのではないだろうか。
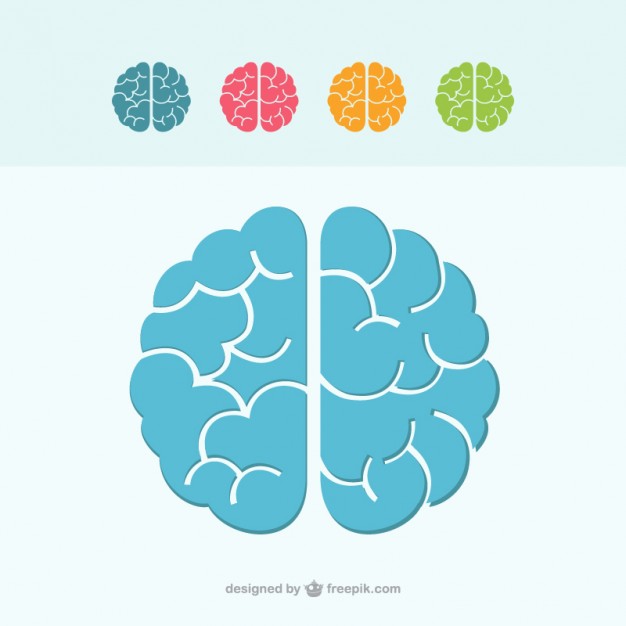
実は、『サヴァン症候群』というキーワードについては、ロンドンブーツの『ベストハウス123』で取り上げられた10数年前から、ずっと引っかかっていた。例えば、足を怪我してしまった人が、松葉づえや手押しの車椅子を使用することになり、腕の筋肉が発達することがあるが、あの現象と、この病気には、何か関連性がないのか、と考えていたのである。そして、たまたま買ったこの本に、まさにこのサヴァン症候群についてこうして書いてあり、私と同じような見解があるのを見た時、今回の黄金律と、『ダムの水路』の話と、これらは無関係ではない可能性が高いと言えるわけである。
総花主義(集中の不能)
東京大学経済学部を卒業後、通産省に入り、日本万国博覧会を企画し、開催にこぎつけた立役者、堺屋太一の著書、『組織の盛衰』にはこうある。
共同体の尺度―③総花主義(集中の不能)
機能組織の共同体化が引き起こす第三の、そしてもっとも一般的な弊害は総花主義、つまり能力均等分散が固定化し、集中が不可能になることである。機能組織が、その本来の目的を達成する為には、臨機に必要な能力―資産、施設機材、人材、情報―を最も重要な断面(職場や事業)に集中することが必要である。しかし、これには当然、重要ではないと判断された部局から不満や苦情が出る。優秀な組織人なら、誰でも自分の担当する分野こそ最も大事と信じているからだ。
(中略)共同体化した組織では、特定の部局や構成員に抱かせることを嫌うので、あえて能力の集中をせず、全部局に総花的な分散が行われる。(中略)この面からも、組織の共同体化は、組織の機能、つまり目的達成能力を決定的に損なうわけである。
つまり、『集中』せずに、『分散』した。すると、それが仇となって組織が衰退した、ということである。
バランスよりも一点集中
人間のお金に対する考え方のパラダイム転換を説いた、ロバート・キヨサキの著書、『金持ち父さん 貧乏父さん』にはこうある。
バランスよりも一点集中
トーマス・エジソンはバランスがとれていなかった。一つのことに集中していた。ビル・ゲイツもしかり。ドナルド・トランプもしかり。ジョージ・ソロスもしかり。ジョージ・パットンは自分の指揮する戦車隊を広範囲に少しずつ配置するのではなく、ドイツ軍の手薄なところに集中させて勝利を収めた。対独放映のために国境に要塞を築きマジノ線を構築したとき、フランスは広くまんべんなく配置する方法をとった。その結果フランスがどうなったかは、皆さんご存知のとおりだ。
もし金持ちになりたいという気が少しでもあるのなら、焦点を絞らなければだめだ。たくさんの卵をごく少ない数の籠に入れる。これが秘訣だ。いつもお金に困っている中産階級の人間がやるようなことをしていてはだめだ。つまり、わずかな卵をいくつもの籠に分けて入れるというのではだめだ。
分散投資せず、『FOCUS』する!
同じくロバート・キヨサキの著書、『お金がお金を生むしくみの作り方』にはこうある。
分散投資せず、『FOCUS』する!
最後に、金持ちになるための心構えについて一言。皆さんに実践してほしいのが、『FOCUS 』(集中)するということだ。それにはふたつの意味がある
ひとつは、投資対象を絞り込むこと。いわゆる投資の専門家は、『リスク分散のために分散投資をしなさい』とアドバイスする。分散投資をすればリスクも分散されるというのが彼らの言い分だ。だが、私が受けた訓練は違っていた。軍隊の学校での訓練により、私たちはフォーカスする、集中することを叩きこまれたし、優秀なパイロットになるために、他のものを犠牲にしてでも訓練に没頭した。タイガー・ウッズだってそうだ。彼は『分散』なんてせず、ゴルフに打ちこんだ。
(中略)もうひとつは、気持ちのうえも『集中』すること。『FOCUS』という単語には、”Follow One Course Until Successful(成功するまで一つのことをやり遂げる)という意味も込められている。

事業でも、投資でも、ありとあらゆる戦略に対し、この法則は通用する。
異彩を放つ人間の共通点
ケビン・メイニーの著書、『トレードオフ』にはこうある。
インターネットの誕生と普及。彗星のようなネットスケープの登場とそれにつづくブラウザ戦争。アップルの不死鳥ぶり。PC業界でのマイクロソフトの覇権と近年におけるその揺らぎ。IBMの凋落と目覚ましい再生。グーグルによる世界の検索市場の席巻。AOLの誕生とタイムワーナーの不幸な合併。モトローラの浮沈と惨状。ロシアにおける民間コンピュータ産業の萌芽。中国におけるインターネットの黎明…。このほかにも何十という壮大なストーリーを追いかけるなか、ケビンはそれぞれの主役たちにインタビューを行い、錯綜した情報のなかから意味を探りあてた。テクノロジー、企業、産業の急速な発展をただ取材したのではない。特筆すべきは、変わりゆく状況を追いながら、同時進行でその本質を見抜いていた点である。
ケビンはこれらの仕事を手掛ける中、ひときわ異彩を放つ取材相手たちについてある結論を導き出した。それら卓越した人々は、慎重に考え抜いたうえで難しい選択をする勇気を持ち合わせているうえ、『何もかもできる』などという錯覚に陥ることなく、自分が抜きんでる可能性のある分野だけに力を注ぐのだ。
ひときわ異彩を放つ偉人たちがみんな辿り着いていた答え。それが『一つのことに集中すること』だ。
いまある計画をやり抜く覚悟
『ユニクロ』を運営するファーストリテイリング社長、柳井正が、『全リーダー必読』と推薦するラム・チャランの著書、『徹底のリーダーシップ』にはこうある。
いまある計画をやり抜く覚悟
最後に、最も勇気のいる行動について述べておこう。それは『ぶれないこと』である。いまある計画をやり抜くのだ。経済が減速し始める前に進行中だった計画の中には、ほとんど意味をなさなくなったり、新たなビジョンや戦略と整合性がとれなくなったものもあるだろう。しかし、長期的には非常に重要な計画もあるはずだ。たとえば、成功すれば、利益率が上がり、新しい顧客層を獲得できるような新たな生産工程や、新製品の開発などである。そういう新事業には投資し続けなくてはならない。それこそが、『投資』であり、『コスト』とは峻別すべきである。
一つのことをやり抜く際に、実に様々な壁が目の前に立ちふさがるだろう。だが、別にそんなことは関係ない。
不可欠となる継続学習
『もしドラ(もしも高校野球のマネージャーがドラッカーを読んだら)』で有名な、ドラッカーの著書、『イノベーターの条件』にはこうある。
不可欠となる継続学習
実際に何を行うべきかは明らかである。事実、何千年の前からとは言わないまでも何百年もむかしから、継続学習への動機づけとそのための規律は知られている。優れた美術の教師、スポーツのコーチが知っている。組織の優れた助言者たちが知っている。彼らは、本人が驚くほどの成果をあげさせる。その結果、教わる者は刺激され意欲を持つ。特に継続学習に必須の規律を伴う訓練に意欲を持つ。
音階の練習は退屈である。それでもピアニストは大家になるほど練習を繰り返す。毎時間、毎日、毎週繰り返す。同様に、外科医も優秀であるほど傷口の縫い目を正確に合わせるための練習を繰り返す。ピアニストは、何カ月も飽くことなく音階を練習する。技能はごくわずか向上するだけである。だがこのわずかな向上が、すでに内なる耳によって聴いている音楽を実現させる。外科医も、何カ月も飽くことなく傷口を縫い合わせる練習をする。指の技能はごくわずか向上するだけである。だがそのわずかな向上が、手術のスピードをあげ患者の命を救う。自己実現の能力とは積み重ねによるものである。

追及するのは『たったの一歩』だ。だがその一歩が、ある時運命を大きく変える。
孔子が歩んだ一つの道
慶応義塾大学を卒業し、慶應義塾高校で教職に就き、同校生徒のアンケートで最も人気のある授業をする先生として親しまれた佐久協の著書、『論語の教え』にはこうある。
身近なことからコツコツと学び、その積み重ねによって仕事や人生の奥義をみきわめよう。
孔子は謙遜ではなく、『自分は天才的な人間ではない』、『独創的な思想家でもない』ことを強調している。では、どうして孔子は当代の大学者として名を知られ、3000人と称せられる弟子を教育するようになれたのだろうか?そうした疑問に対して孔子は、自分は『下学して上達する』方法をとったからだと解説しているのだ。
わたしたちは、子供の頃には花形スポーツ選手になってみようとか、ノーベル賞をとってみようと夢見ることができるが、長ずるに従い、花形スポーツ選手になれるのは特殊な身体能力の持ち主だけ、ノーベル賞は一部の天才の専有物だと決めつけて諦めてしまう。しかし孔子はそうした諦めを諫めているのだ。孔子は、
『わたしは物知りでもないし、記憶力がよいわけでもない。だからこの一つの道をコツコツと歩み、どうにか人に教えられる立場に立てたのだよ』と述べているのだ。
シェア6倍の逆転劇
また、中国古典研究家、守屋淳の著書、『孫子』にはこうある。
シェア6倍の逆転劇
覚えていらっしゃる年輩の方も多いと思うが、1980年代の半ばまでビール業界はキリンが寡占に近い形をとっていた。最大シェアでなんと63%。サラリーマンのお父さんが癒えに変えると、まずはキリンのラガーを一杯というのが当時の典型的な日常だったのだ。一方、アサヒはシェアが9%を切ってしまい、明日潰れてもおかしくないという状況まで追い詰められてしまう。このときアサヒの人たちは、
『このままキリンと同じ土俵で戦っていては勝ち目がない。他の土俵に『選択と集中』をかけよう』
と決意する。この逆転劇の中心人物の一人だった当時の副社長・中条高徳さんの、次のような述懐がある。ちなみに最初の引用は『孫子』諜攻編の一節で、『準備ができている状態で準備ができていない敵を待ち受ければ勝てる』との意味だ。
≪虞を以って、不虞を待つ者は勝つ。
この利を応用すれば、キリンはラガー(熱処理したビール)では圧倒的だが、『生』に対する用意はほとんどできていない。それどころかキリンの上層部は、『生』は邪道だと唱えているほどだから、『生』に対する戦略があるはずもない。すなわち、『生』に一点集中すればいいと判断できる≫
われわれはいま、ビールは生で飲むのが当たり前だと思っているが、80年代の半ばまで生ビールのシェアは全体の2割しかなかった。なぜならば一番売れていたのがキリンのラガービール(加熱処理したビール)だったからだ。この決断の結果、発売されたのが有名なスーパードライだった。1987年のことだ。これが売れに売れて、6倍以上の差がついて社が十数年かけて逆転してしまう。

一点集中することの恩恵を知れ。
一万時間と七千五百時間
ハーバード大学大学院にて心理学の博士号を取得した、ダニエル・ゴールマンの著書、『EQ こころの知能指数』にはこうある。
反対に、熱意や自信などプラスの動機付けは目標を達成するうえで大きな役割をはたす。オリンピック選手、世界的な演奏家、あるいはチェスのグランド・マスターを調べてみると、彼らには自分自身を叱咤激励して毎日のきびしいトレーニングを続けていく能力が共通していることがわかる。
(中略)今世紀のバイオリンの巨匠といわれる演奏家たちは、5歳ごろからバイオリンを手にしている。チェスでも、世界レベルのチャンピオンは平均7歳ごろからチェスの手ほどきを受けている。10歳でチェスを始めたプレイヤーは、国内チャンピオンどまりだ。小さいうちから訓練を始めるかどうかが一生の差になる。ベルリン最高の音楽学校でバイオリン科トップの生徒はみな20歳をすぎたばかりだが、生涯練習時間は一万時間に達している。二流レベルの生徒は、生涯練習時間が七千五百時間程度だ。
そして、一つに集中するだけでは駄目だ。そこに『費やす』、つまり、『費やした』と胸を張って言えるだけの『実際の費やし』がなければならない。
狭いから失敗するのではなく広いために失敗
早稲田大学を経て、情報会社・出版社の役員を歴任した岬龍一郎の著書、『言志四録』にはこうある。
いまの学者は、学問が狭いから失敗するのではなく、広いために失敗している。また、その学問が偏っているから失敗するのではなく、追及の仕方が浅すぎて失敗するのである。
手を広げすぎることもいけないが、かといって重箱の隅をつつくような専門バカもこまる。現在はスペシャリストは多いが、総合判断力のあるゼネラリストがいないのが実情である。
『一点集中』、『十分に費やす』。この2点だ。
脳の変化
栄誉ある賞を多々受賞し、卓球選手としてオリンピックにも2度出場し、オックスフォード大学を首席で卒業したマシュー・サイドの著書、『非才』にはこうある。
脳の変化
さらなる研究で、同じく注目に値する結果が発見された。 ロンドンのタクシー運転手──免許証を取得するには、厳しいことで有名な試験に合格しなければならない── についての研究で、彼らの空間ナビゲーションをつかさどる脳領域は、タクシー運転手以外の人たちよりもかなり大きく、またその領域は、仕事の経験に応じて成長を続けることがわかったのだ。
脳の変化において重要な役割をになうのは、神経線維を覆う『ミエリン』という物質で、これは脳内の信号伝達速度を飛躍的に向上させる。コンサートピアニストの脳スキャンを行った2005年の実験では、練習にかけた時間とミエリンの量に比例関係が認められた。だが、脳の変化という物語のテーマは、ミエリンだけではない。 目的性訓練は、向上を求める中で新たな神経接続を作りだし、 脳の特定部位を増大させ、このためエキスパートは改善を探求するなかで、 脳の新しい領域を利用できるようになるのだ。
(中略)これで、知識構築のプロセスそのものが、知識を蓄えて処理する ハードウェアすらも変えてしまうことがわかった。 非常に高度なソフトウェアをダウンロードする過程で、 コンピュータの内部回路が奇跡的に初代ペンティアムからペンティアム4に アップグレードされるようなものだ。
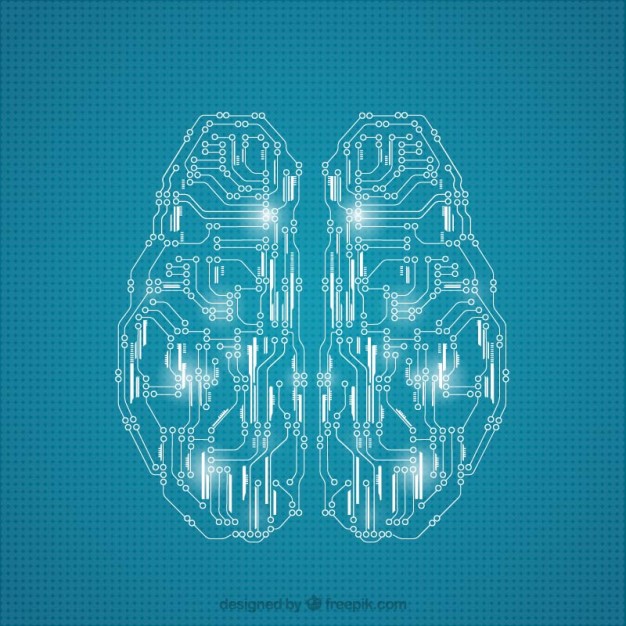
『天才の仕組み』にも書いたが、この『ミエリン』と『脳領域』の事実は、今回の黄金律に密接に関係している。
可塑性(かそせい)が広げる能力の可能性
東京大学大学院教授、池谷祐二の著書、『脳と心のしくみ』にはこうある。
可塑性(かそせい)が広げる能力の可能性
人の場合、感受性期は多くのケースで9歳くらいまでと考えられている。感受性期を過ぎてから、さらに神経細胞がつながり、20歳の頃、脳神経のネットワークが完成する。その後は成長が止まってしまうのかというと、そうではない。それ以降も学習や経験を生かして新しい脳のネットワークをつくっていく。このように脳が生涯にわたり変化することを脳の『可塑性』といい、人は人生で得た、いろいろな経験や知識を脳回路に蓄えることで、ネットワークをカスタマイズしていくのだ。
可塑性があることは、個人の可能性を広げる。つまり、生まれた瞬間は、遺伝子で決まる能力に圧倒的に左右されるが、脳に可塑性があることで、学習や訓練によって先天的な不利を覆し、脳が健康である限り、脳力を付け加えていくことが出来るのである。熟練した職人の技術はまさに、脳の可塑性によって新しいネットワークが構築されることで獲得できるのだ。
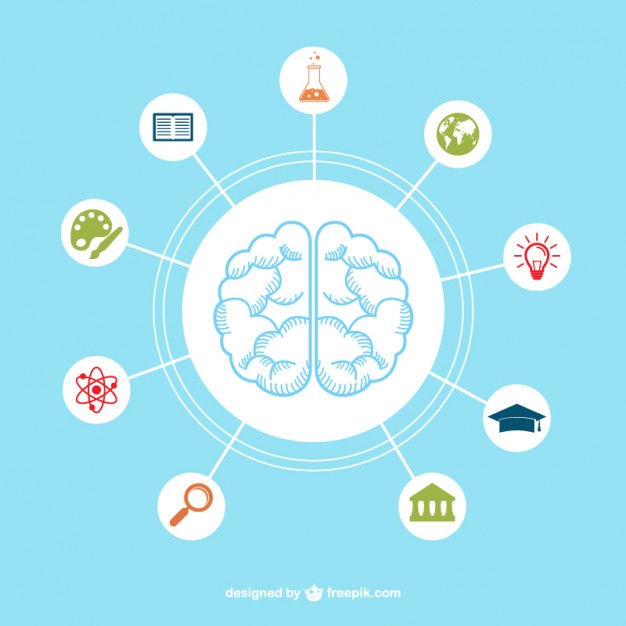
これは『非才』にある内容と同じ的を射ている。
才能とは、同じ情熱、気力、モチベーションを持続することである
天才棋士、羽生善治の著書、『決断力』にはこうある。
才能とは、同じ情熱、気力、モチベーションを持続することである
以前私は、才能は一瞬のきらめきだと思っていた。しかし今は、10年とか20年、30年を同じ姿勢で、同じ情熱を傾けられることが才能だと思っている。直感でどういう手が浮かぶとか、ある手をぱっと切り捨てることができるとか、確かに個人の能力に差はある。しかし、そういうことより、継続できる情熱を持てる人のほうが、長い目で見ると伸びるのだ。
(中略)周りのトップ棋士たちを見ても、目に見えて進歩はしていないが、少しでも前に進む意欲を持ち続けている人は、たとえ人より時間がかかっても、良い結果を残しているのである。
一つのことに集中し、同じ情熱を何十年も注ぎ続ける。『それが当たり前だ』という覚悟たる初期設定を持てるかどうかが、人間の運命を大きく左右する。
10年ルール、1万時間の法則、クリティカル・マス、量質変化
また、ここで確認すべきなのは、以下の概念である。
10年ルール、1万時間の法則、クリティカル・マス、量質変化。
[memo title=”10年ルール”]『世界レベルの業績に達するまでに少なくとも10年かかる』という法則。[/memo]
[memo title=”1万時間の法則”]『人が何かに習熟してスペシャリストになるまでにかかる時間』を示唆した法則。[/memo]
[memo title=”クリティカル・マス”]『量が積み重なって、質的な変化を起こす臨界点』を指す言葉。[/memo]
[memo title=”量質変化”]『量が積み重なると、あるとき質的な変化を起こす現象』の意味。[/memo]
人間が、『量を積み重ねて質的な変化を起こす』、『クリティカル・マス』を超える為には、『1万時間』、及び『10年』という時間をかけて、それに特化して努力し、集中する必要がある。これらの事実は、この黄金律の価値を強化する重要な要因となっている。
特化した一流アスリートたち
一つのことに集中する。例えば日本で言えば、イチロー、本田圭佑、錦織圭、吉田沙保里、石川遼、内村航平、福原愛、浅田真央、羽生結弦、彼ら、彼女らは皆若くして世界に名を馳せる、名アスリートとなったわけだが、それは、彼ら、彼女らが幼少の頃から、自分の生きる道をしっかりと見定め、野球、サッカー、テニス、レスリング、ゴルフ、体操、卓球、フィギュアスケートと、そのことだけを考え抜いて、努力して生きて来たからだった。

偉人にあったもの、なかったもの
また、彼らのように『望んで』一つのことに集中した人間だけではなく、違う方法で結果的にそうなった人の話も見逃すことはできない。挙げたらキリがないが、例えば、宅配ピザの市場で2位に圧倒的な差をつけてシェア1位(売上高432億円、12年度見込み。全国552店舗)を取る『ピザーラ』を運営する『フォーシーズ』の社長、淺野秀則は、そこに到達するまでに実に幾多もの失敗を積み重ねて来た。例えば、運営していたクラブが火事になり、半年以上も入院生活を余儀なくされたのだ。
そういう失敗が何度もあった。そして宅配ピザに辿り着いた。彼に『あった』ものは『不撓不屈の精神』だが、逆に『無かった』ものは、一体なんだと思うだろうか。また。『つるとんたん』で有名なカトープレジャーグループの社長、加藤友康は言った。
『父が病気になり、入退院を繰り返すようになったんです。とたんに商売も上手くいかなくなりました。うどん屋も、洋装店もだめ。気づくと借金しか残っていない状態でした。』
そのとき、父親の商売を引き継げるのは3男の加藤しかいなかった。それは同時に20億円の負債を引き継ぐことも意味した。彼に『あった』ものは『不撓不屈の精神』だが、逆に『無かった』ものは、一体なんだと思うだろうか。

世界的に有名な高級ブランド『シャネル』の生みの親、ココ・シャネルは、12歳という若さで母親に死なれ、父には捨てられ、孤児院生活を強いられた。 恵まれない状況から、不撓不屈の精神でノーベル賞を受賞した幾人もの学者たちはどうだ。世界的に複雑な目で見られるユダヤ人はどうだ。世界で一番ノーベル賞を取っている人種は、ユダヤ人だ。
今の世で言えば、Google創業者のラリー・ペイジとセルゲイ・ブリン、Facebook創業者のマーク・ザッカーバーグ、デル創業者のマイケル・デル、インテル創業者のアンドリュー・グローブ、マイクロソフトCEOのスティーブ・ハルマー、スターバックス中興の祖ハワード・シュルツ、ブルームバーグ創業者のマイケル・ブルームバーグ。
モーセ、マルクス、フロイト、彼らは皆、ユダヤ人である。だがユダヤ人は、かつてのナチスが考えたような、悪の人種などではない。むしろ、『そういう劣悪な環境』を強いられ、世界中に飛び散らされ、その環境の中で生きていくしかなかった。

一所懸命
また、2016年1月23日、岡村隆史のインスタに掲載された松岡修造の言葉は、第3の黄金律である『生きるのは過去でも未来でもない。『今』だ。』とピタリ同じ内容だったが、よくよく見ると、このページにはもう一つの黄金律が隠されていた。
「一つの所に命を懸けなさい」
僕は、小学校時代の先生にいただいた 「一所懸命」という言葉が大好きです。今もこの言葉が僕の中心にあるから、何をするにも一所懸命。過去を振り返ると後悔したくなり、未来を考えると不安になる。だから今、この瞬間に全精力を傾けるのです。 この一所懸命の積み重ねが、未来の自分をつくってくれる。僕はそう信じています。
中居正広は言った。
『若い頃は、汗かけ、物かけ(欠け)、恥をかけ、という精神でやってきた。』
明石家さんまは言った。
『私の人生のどん底は、離婚とバブルが弾けた時。負った借金も、中途半端ならいろいろな選択肢があったかもしれないが、幸か不幸か、自分に課せられた借金が半端な額じゃなかった。喋るか、死ぬかという二択しかなかったらそりゃ、喋るのを選択するでしょ。』
彼ら、彼女らに『あった』ものは『不撓不屈の精神』だが、逆に『無かった』ものは、一体なんだと思うだろうか。
一意専心
また、私はある日の『さんまのまんま』の明石家さんまの発言を聞き逃さなかった。私も長い間彼を見てきたつもりだったが、私がそれを発言するのを見たのは初めてだった。
さんまは、好きな四文字熟語は何かと尋ねられ、こう言った。
『『一意専心。』その次が、『大器晩成』。』
松下幸之助は、本田宗一郎は、盛田昭夫は、井深大は、稲盛和夫は、永守重信は、鈴木修は、孫正義は、
彼らに『あった』ものは勇往邁進(ゆうおうまいしん。恐れることなく、自分の目的・目標に向かって、ひたすら前進すること。)に突き進む、『不撓不屈の精神』。そう考えると、、逆に『無かった』ものは、一体なんだと思うだろうか。
・NEXT⇒(一致する偉人の名言)
・⇐BACK(簡潔に)